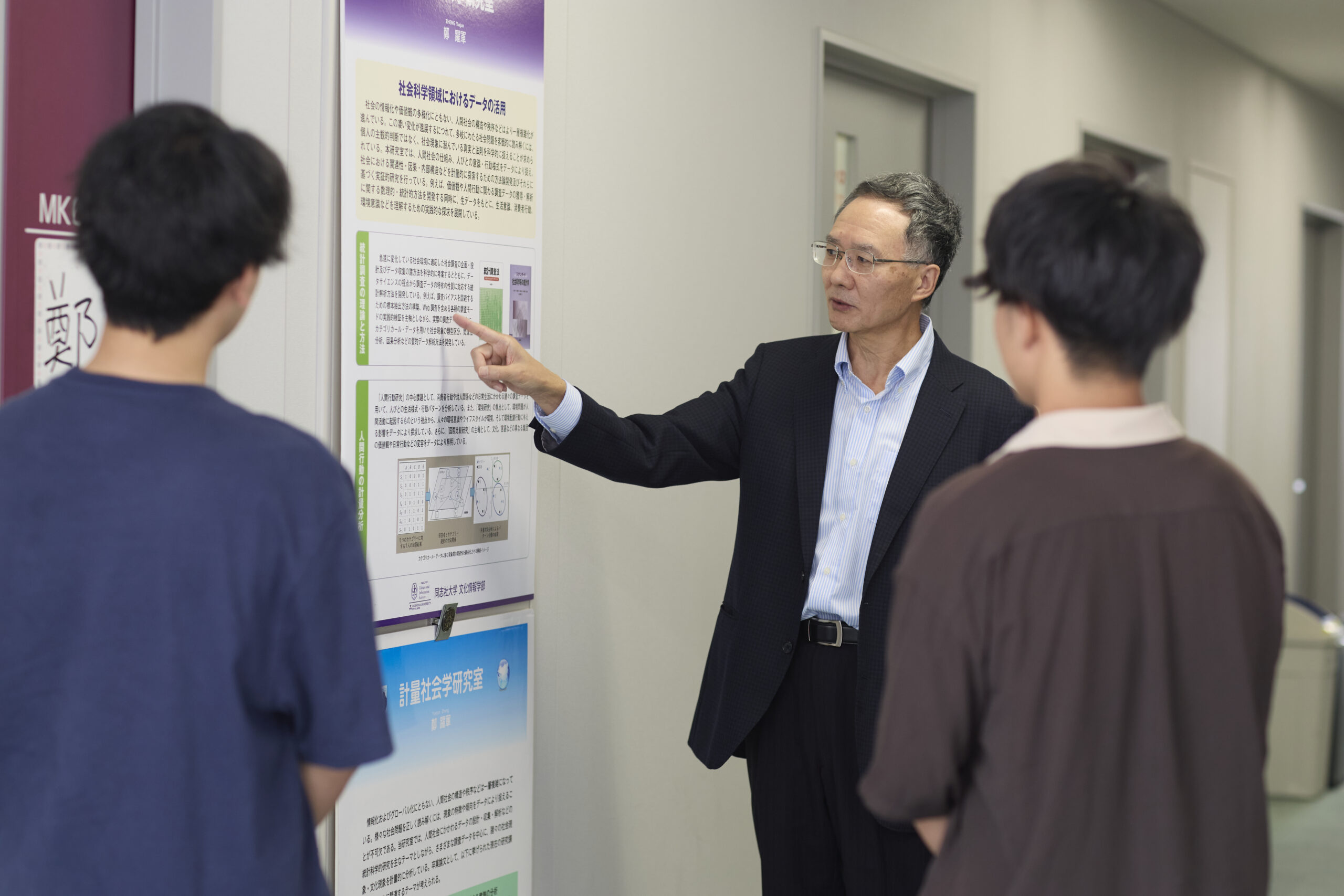FACULTY MEMBERS

複雑化する文化や社会の現象は、直感や想像だけでは理解できません。データに親しみ、使いこなして私たちの生活を読み解いていきましょう。
FACULTY MEMBERS
計量社会学研究室
鄭 躍軍
博士後期課程教授
統計科学、社会学、環境政策・環境配慮型社会
PROFILE
1995年東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了。農学博士。統計数理研究所助教、総合研究大学院大学助教、総合地球環境学研究所准教授を経て、2009年より現職。米国ニュー・ハンプシャー州立大学客員教授、国立台湾大学客員教授を歴任。専門は統計科学、社会調査論、計量社会科学。専門社会調査士。社会調査理論と調査データ解析方法の構築とともに、価値観、消費者行動、意識の国際比較調査など、幅広い研究活動に取り組んでいる。
『データサイエンス入門』『社会調査データ解析』『社会科学系の統計学』『統計調査法―社会科学のためのデータサイエンス』など著書多数。
人々の意識や行動様式から文化や社会の諸現象を探る
一つの問いから見えるそれぞれの社会の特徴
生まれ変わるなら男?それとも女?これは、1953年以来統計数理研究所が行っている「日本人の国民性調査」の設問の一つです。男性はいつの時代も約9割が「男」と答え、女性も1960年代後半までは約7割が「男」と回答していました。状況が変化したのは1973年。「女」と答える女性の割合が増え続け、2018年には7割に至りました。
ここで中国や韓国など近隣国に目を向けると、依然、女性の約半分は「男」と答えています。なぜ日本では逆転し続けているのか。女性の社会的地位の向上や自己評価の高まりなど、日本社会で起こっている諸事象に関連づけて、真実が何かを明らかにすることが大切でしょう。
このように、人々の意識・行動様式や人間社会の仕組みを客観的データで捉え、さまざまな視点から文化・社会現象を解き明かしていくのが計量社会学という学問です。
ここで中国や韓国など近隣国に目を向けると、依然、女性の約半分は「男」と答えています。なぜ日本では逆転し続けているのか。女性の社会的地位の向上や自己評価の高まりなど、日本社会で起こっている諸事象に関連づけて、真実が何かを明らかにすることが大切でしょう。
このように、人々の意識・行動様式や人間社会の仕組みを客観的データで捉え、さまざまな視点から文化・社会現象を解き明かしていくのが計量社会学という学問です。
環境を意識はしても、行動に移さない日本人
また、日本におけるある環境意識調査では、地球温暖化に関して7割以上の人が「対策が必要」と答えました。さらに、「文化、経済、科学技術、環境」のうち国際交流において優先すべきものを問う設問では、「環境」を選んだ人が最も多くいました。
こうした考えとは裏腹に、グリーン製品の購入、節電や節水、ゴミの削減など環境行動に取り組む割合は低く、3割どまり。経済を優先する韓国、科学技術を優先する中国にすら追い抜かれています。つまり、「日本人は環境への意識は高いが、行動は他国に劣る」という結果。こうしたデータは今後日本人が環境のために何をなすべきか、如何に人びとの環境配慮行動を喚起すべきかを考えるヒントになるでしょう。
こうした考えとは裏腹に、グリーン製品の購入、節電や節水、ゴミの削減など環境行動に取り組む割合は低く、3割どまり。経済を優先する韓国、科学技術を優先する中国にすら追い抜かれています。つまり、「日本人は環境への意識は高いが、行動は他国に劣る」という結果。こうしたデータは今後日本人が環境のために何をなすべきか、如何に人びとの環境配慮行動を喚起すべきかを考えるヒントになるでしょう。
個人の意識と集団の在り方
当研究室では、人間社会の仕組み、日常生活における人々の意識や行動様式を調査データに基づき分析しています。どのようなデータをどのように収集していくのか、という理論的な研究だけでなく、既存のデータを中心に、人間社会の仕組みを理解する応用的な研究テーマも扱います。卒業生の研究テーマは、「統計調査の理論と方法」「消費者動向」「ライスタイルと環境問題」など。学生を指導する際は、それぞれの個性を生かすことを心掛けています。皆さんには、チャレンジ精神が芽生える独自の発想を持って、データを中心とした実証的研究に挑んでほしいですね。