FACULTY MEMBERS
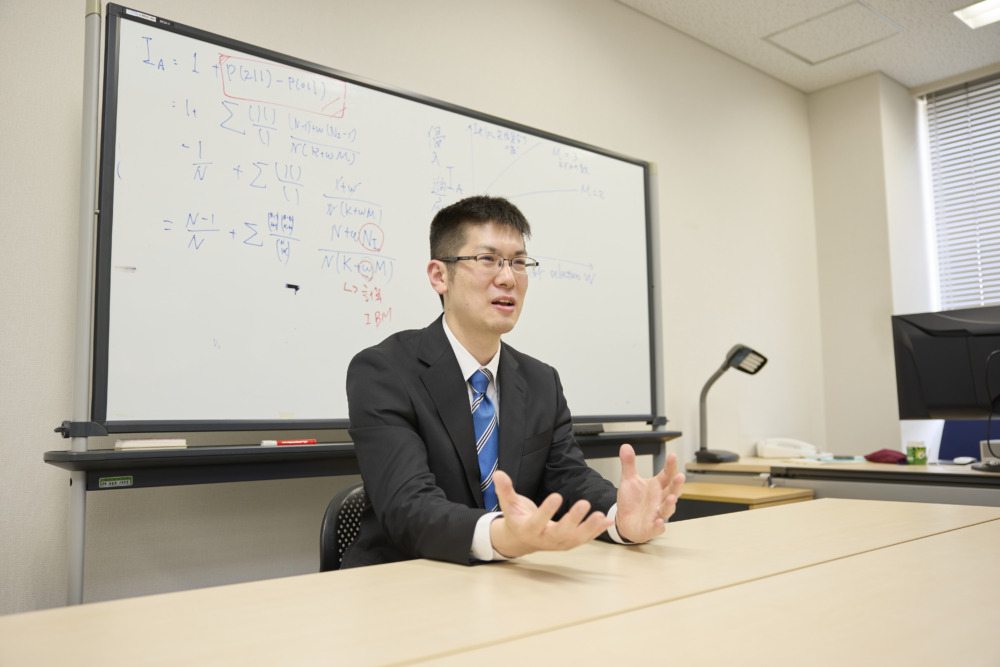
文系も理系も関係ない。自由な発想と手段だからこそ、未知の領域を解き明かせる
民間伝承からハエまで。人間の文化をユニークな研究手法で追及する
「祟り」の伝承が森を守る?数理モデルで文化と環境の関係を解き明かす
文化進化(学習による情報の伝播)や生物進化(遺伝子による情報の伝播)が、周囲の環境や生き物とどのように影響を及ぼし合っているのかを解明することが私の研究です。研究ではさまざまな手法を使いますが、その一つは、複雑な生物現象や文化的な情報を数理モデルにまとめて解析することです。例えば、「木を切ると森の神様が怒る」といった民間伝承や宗教的な教えを聞いたことはありませんか。このような信仰があると自然環境の豊かさにつながるのではないかと考えられますが、どのような場合に信仰によって豊かな自然環境が維持されるのかを数理モデルで解析したことがあります。その結果、伝承が伝える祟りの恐ろしさ(例えば、木を伐採すると村が滅びる)と信仰の広まりやすさ(伝承を信じる人の増えやすさ)、この二つの要素によって豊かな自然環境の維持されるかが決まるということがわかりました。
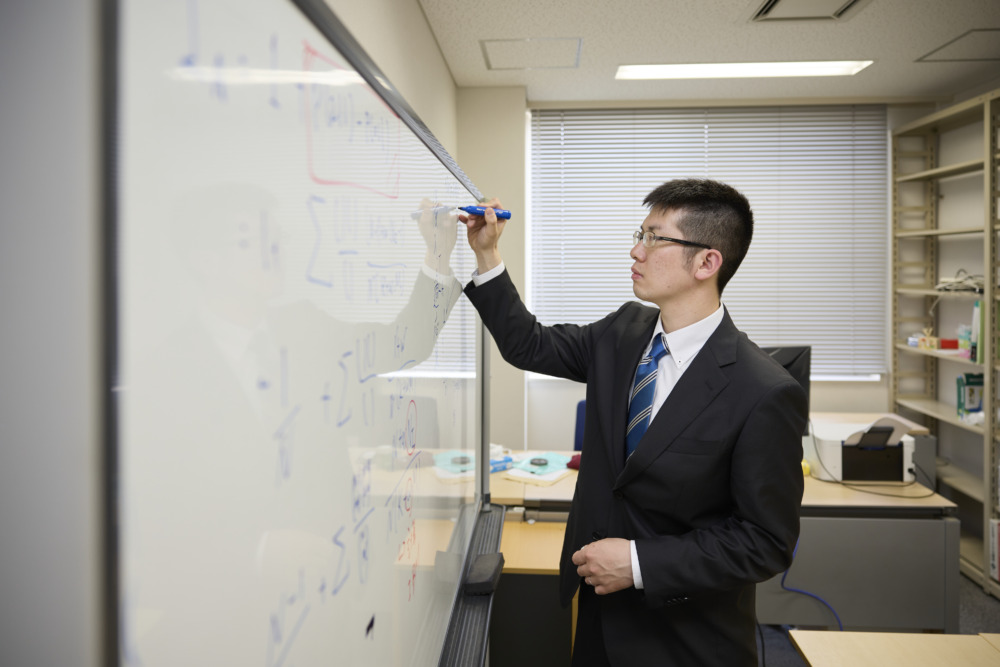
文化の移ろいを解き明かす鍵は、まさかのハエ!?
「文化はどのように変化するのか?」非常に興味深い問いですが、人間を実験対象にすることには、時間的・経済的・倫理的に大きな制約があります。では、どうしたらよいのか?私が文化進化を探るための実験対象として選んだのは、キイロショウジョウバエでした。近年の研究では、人間以外の動物にも文化があると報告されているうえ、ハエは世代交代が早く、人間では難しい長期的な実験を短期間で行うことが可能なのです。実験の結果、「このような文化が形成されるとハエの個体数が増える」といった発見があれば、同じような文化が人間の人口サイズの増大にも影響する可能性が考えられます。人間だけを研究対象にしていては見えない文化進化の全体像を、制約に縛られず広い視野で深く理解することを目指しています。
「文系だから」「理系だから」は関係なし!研究は自由で面白い
私はもともと文系の学部に入学しましたが、文化を勉強するうちに人間の生物学的側面に興味を持ち、理系へと分野を変えました。その後の研究生活では、数理モデルからデータベース解析や実際の生き物を使った実験まで、様々なアプローチを試してきました。振り返ると、自由で積極的な挑戦を繰り返してきたと思います。皆さんにも「自分は〇〇だから」といった枠にとらわれず、興味のあることには自由に積極的に挑戦してもらいたいと思います。文化情報学部はそういったチャレンジができる学部です。まだ見ぬ新しいアイディアを持つ学生との出会いを、心から楽しみにしています。
