FACULTY MEMBERS

「文化の記憶」に誰もが自由にアクセスできる環境を。文化情報と子どもたちが出会う感動の瞬間が、研究のやりがいです。
FACULTY MEMBERS
デジタルアーカイブ・情報活用研究室
大井 将生
学部准教授
教育学、図書館/博物館情報学、情報デザイン
PROFILE
三重県出身。高等学校教諭, 東京大学大学院情報学環 特任研究員, 人間文化研究機構 / 国立歴史民俗博物館特任准教授等を経て, 現職。文部科学省, 文化庁, 内閣府 等の委員を歴任。
「デジタルアーカイブの教育活用」を主なテーマとして情報学やデジタルヒューマニティーズの視座から学校教育を対象とした実践的研究に従事。主な研究に「ジャパンサーチを活用したキュレーション学習」「S×UKILAM(スキラム)連携」「学習指導要領LOD」「荘園LOD」「DHの中等教育への拡張」等。
子どもたちの心からの「問い」をデジタルアーカイブでつなぐ
文化の記憶を未来へ。目指すのは「タイムマシーン」×「どこでもドア」
世界中で生まれては消えていく、大切な文化や記憶。私はこうした文化情報を社会と未来に繋ぐため、「デジタルアーカイブ(DA)」の構築とその活用方法を包括的に研究しています。多様なデータを長期保存することを使命とするDAは、過去の資料にも物理的に離れた場所にある情報にもアクセスできます。それは例えるなら時間と空間の壁を飛び越える「タイムマシーン」であり「どこでもドア」でもあると言えます。現代では、Web上に溢れる膨大な情報の海から、信頼できる「ホンモノ」に主体的にアクセスし、自在に活用できる環境やリテラシーの育成が求められています。そこで私は、国や自治体、文化施設や研究機関、企業・NPOなどにストックされてきたDAの文化情報をフロー化し、社会と未来へ繋ぐことでコミュニケーションを創発する、新しい情報デザインのあり方を検討し続けています。
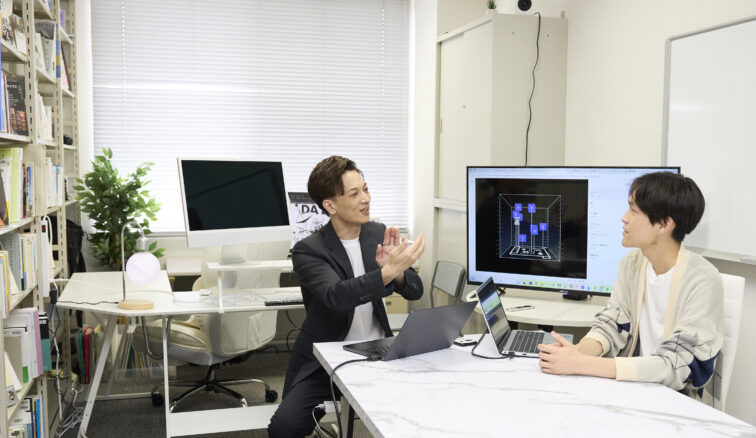
「問い」と文化情報を繋ぐ「キュレーション」と「S×UKILAM」
GIGAスクール構想で一人一台端末が配られ、ICT教育の基盤は整いつつあります。しかし、「デジタル技術で何をどのように学ぶか」という課題は残ったままです。そこで私は、子どもたちが自身の「問い」を起点としてDAを活用する新しい探究方法として「キュレーション学習」を提案しています。例えば、国の統合型DAである「ジャパンサーチ」と子どもたちの学びを繋ぐ仕組みを開発し、教育現場に導入しました。子どもたちが心から「知りたい」と思ったことについて、DAから主体的に情報を探し出し、自分の言葉でまとめ、新しい知識を仲間と創り上げる過程は、まさに学びのイノベーションが生じる場でした。また、そうしたDAを活用したワクワクできる新しい学びを共創・共有していく枠組みとして、学校だけに閉じるのではなく、先生や司書・学芸員・アーキビスト・自治体や企業の関係者らが協働する「S×UKILAM」連携というスキーマを構築しました。2025年4月現在、46都道府県から488機関の学校や機関・企業などが参画するコミュニティになっており、様々な化学反応が創発されています。
感動の「共振」が研究のやりがいに
研究で最もやりがいを感じるのは、子どもたちがDAを活用して出会った新たな発見に目を輝かせ、前のめりに学びに向かう場に立ち会うことです。それがクラス全体で生じると、教室空間が震え、気づいたら涙が出てくるような瞬間があるのです。私はこのような感動をDAによる「共振」と呼んでいます。何百年も過去から届いた情報が、現代の子どもたちの心を強く揺さぶる、時空間を超えた共振。彼らの感動が、DA構築に尽力した人達や指導にあたった先生方の想いと深く結びつく心の共振。過去、現在、未来、そして人々の想いが繋がり、響き合うこの感動的な瞬間に、私は研究を続ける意義を見出しています。
